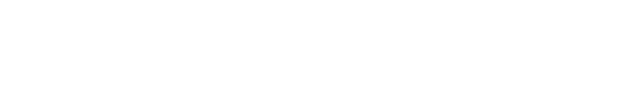尿路感染症
尿路は腎臓、尿管(腎臓から膀胱に流れる尿が通過する管)、膀胱、および尿道で構成されます。通常、健康な人では、尿路は無菌(細菌などの感染性の微生物が存在しない状態)ですがどの部分にも感染がおこる可能性はあり、尿路で発生した感染症を尿路感染症(UTI)と呼びます。また、尿路感染症は、尿路内の感染部位に応じて、上部尿路感染症(腎盂腎炎)と下部尿路感染症(膀胱炎、尿道炎、前立腺炎)に分類されます。
感染症を引き起こす微生物が尿路に侵入する経路は2つ考えられます。そのうち格段に多いのは尿道からの侵入経路です。尿道から侵入した微生物は、尿路を上の方に移動して膀胱に達するほか、ときには腎臓にまで到達して、膀胱と腎臓の両方に感染する場合もあります。もう1つの侵入経路は、微生物が血流から、通常は腎臓へと侵入するものです。
尿路感染症は、そのほぼすべてが細菌によるもので、大腸菌が最も多い原因菌です。ウイルス、真菌または寄生虫が原因になる場合もあります。
膀胱炎
膀胱炎とは、おしっこの出口(外尿道口)から入り込んだ細菌が尿の通り道(尿道)を通って膀胱で繁殖し、膀胱の内側の粘膜に炎症を起こす病気のことです。
膀胱炎は、ほとんどの場合、大腸菌をはじめとした大腸・直腸などに住んでいる腸内細菌が原因菌であることが多く、これらの細菌が尿道から侵入して、膀胱で増殖することによって起こります。
他に、多くはないですが一部の抗アレルギー薬や抗がん剤などによる薬剤の影響でおこる膀胱炎や放射線治療の副作用で発症する膀胱炎もあります。
細菌が原因でおこる膀胱炎で、基礎疾患がない場合は単純性膀胱炎といい女性に起こりやすいタイプです。急に頻尿や残尿感、排尿痛、排尿終わりの痛みなどの症状が現れます。
免疫力が低下した状態で発症しやすくなりますので以下のような状態には注意が必要です。
- 尿意を我慢する(我慢することが多い)
- 冷え症がみられるが対策はしない
- ストレスや精神的な負荷、考えごとを抱え込んでしまっている
- 肉体的・精神的にも疲労が蓄積している状態
- 過度なダイエットで体力の消耗がみられる など
ほかに、妊娠や性交渉、月経が誘因となって発症することもあります。
尿路もしくは全身に基礎疾患があり慢性的におこる膀胱炎を複雑性膀胱炎とよびます。
単純性膀胱炎より症状は比較的軽いことが多いですが、根本的な原因が解決されない限り繰り返し発症するリスクがあります。
尿路にカテーテルなどの異物がある場合や、膀胱癌、尿路結石、前立腺肥大症や神経因性膀胱などによる排尿障害、尿路の先天的な構造異常などが原因となります。また、全身の抵抗力が低下するような疾患がある場合も尿路感染症を繰り返してしまいます。
膀胱炎を繰り返す場合は、これらの基礎疾患を改善しないかぎり完全に治癒することは難しいため是非いしだクリニックきたすずまでご相談ください。
腎盂腎炎
腎臓で作られた尿が流れてきて集まる腎盂や、その周囲組織が細菌に感染して炎症が起きた状態を腎盂腎炎といいます。
原因のほとんどは、細菌が尿路をさかのぼって起こるため、腎盂腎炎は膀胱炎のあと左右どちらかの腎臓に起こることが多いです。
男性より女性のほうが頻度は高いですが、前立腺肥大症や尿路結石症があり尿路が閉塞していることで腎盂腎炎になりやすくなることもあり男性にも注意が必要です。
膀胱炎でも出る排尿時の痛み、頻尿、残尿感、尿の濁りなどの症状に加え、発熱や全身のだるさ、悪寒戦慄、腎盂腎炎の特徴である背中や腰の痛みなどの症状があらわれます。
また、吐き気や嘔吐などの消化器症状が出ることもあります。
結石や腫瘍が原因となっている場合には血尿が見られることもあります。
多くは抗生物質(抗菌薬)をはじめとする適切な治療で治りますが、早期に適切な治療を行わなければ、炎症が全身に広がって敗血症という状態になります。
敗血症は急激な血圧低下や多臓器不全を起こし、生命が脅かされる危険のある状態です。
膀胱炎症状のあとに悪寒や震えがくるほどの高熱や、左右どちらかの背中や腰の痛みが見られた場合はぜひ早めに受診してください。
急性前立腺炎
急性前立腺炎は、前立腺に細菌が感染した尿路感染症です。
高熱、悪寒戦慄にくわえて尿意切迫感、頻尿、排尿痛、残尿感、血尿など膀胱炎に似た症状をきたします。いつもより尿が出にくい排尿困難感や、会陰部(陰のうと肛門のあいだ)の痛みがでることもあります。
腎盂腎炎と同様、放っておくと、敗血症を発症し、重症化して生命を脅かす危険もありますので速やかな治療が必要です。
抗生物質での治療に加え、十分に水分を摂り、尿と一緒に細菌を排出することが必要です。前立腺肥大症を伴う場合は排尿障害が増悪し、余計に炎症が悪くなる悪循環が起きやすいため前立腺肥大症の治療も行うほうが望ましいです。
自転車やバイクでの前立腺への刺激やアルコール摂取で炎症が悪くなる可能性があるため治療中は控えてください。
尿道炎
尿道炎とは、おしっこ(尿)の通り道である尿道に、病原菌が感染し、炎症が引き起こされる病気です。主に性行為により感染するクラミジアや淋菌などが原因菌のことが多いですが、
尿道炎=必ずしも性感染症(STI:Sexually Transmitted Infection)であるとは限りません。
尿道炎は男性に多く、以前は性風俗店の利用などで感染する場合が多いといわれていましたが、最近は身近なところでの無症状の感染者も増えており、幅広い年齢層、患者層で感染が確認されています。
女性は男性と比較すると尿道が短く、女性の場合、尿道炎は膀胱炎と同時に発症するため、尿道炎のみでは診断されません。また、性行為を介した感染の場合、女性では子宮頸管炎として診断されるケースが多くなります。
潜伏期間は、淋菌感染の場合2~7日間で比較的早く症状が現れます。クラミジア感染の場合1〜3週間で、症状がないこともあるため感染時期が分からないこともあります。
また、オーラルセックスなどでも感染することがあり、尿道の他、のど(咽頭)や眼などにも感染し炎症を起こすこともあります。
排尿時の違和感、かゆみ、むずむず、ヒリヒリする、排尿痛、尿道から膿や分泌物がでるなどの症状がみられます。
尿道炎の治療は、主に原因菌に対する抗生物質の投与を行います。
また医師の指示に沿って水分をたくさんとってください。
抗生物質を服用しても治りがよくない場合には、抗生物質の種類を変更します。
尿道炎の予防には、感染予防のためコンドームを装着することの重要性や、オーラルセックスだけでも感染することをパートナーにも理解してもらうことが必要です。